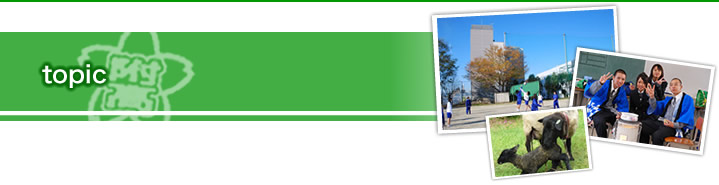
2024年6月19日 by admin
グローバル・スタディーズⅠを行いました
〇日 時 令和6年6月19日(水)
〇場 所 大講義室、中講義室、化学室
〇対 象 第2学年
〇講 師 愛媛大学教育学部学生支援機構 村田晋也先生
本日のグローバル・スタディーズⅠは、愛媛大学教育学部学生支援機構の村田晋也先生と4人の大学生に授業をしていただきました。4回シリーズの最後の授業となった今回は、大学生たちの海外経験のお話を聞くことが出来ました。一人目は「台湾」「サイパン」にリーダーシップチャレンジプログラムを通して行った方のお話でした。海外の同じ大学生と触れ合う楽しさ、小中学生に英語でプレゼンする難しくもあり、楽しかった思い出をお話してくれました。二人目はインドネシアに行った方でした。日本とは全く異なるイスラム教の生活スタイルだったが、とても楽しかった思い出をお話してくれました。三人目は、ボランティアを通じて知り合ったカナダ在住の人を頼りにアメリカ、カナダに行ったお話、その後フィンランドやオランダへの旅行を含め「僕のやりたいこと」と題してお話をしてくれました。四人目はサイパンにリーダーシップチャレンジプログラムで行ったお話をしてくれました。小学校で運動会をプレゼンしてとても盛り上がったお話をしてくれました。
大学生の一人から「行った経験が何より大切。迷ったら飛ぼう!意外と海外行けちゃいます。」と言葉を頂きました。日本とは全く違う海外での生活が人生を楽しく、そして人間を大きくしてくれたという話をしてくれました。生徒たちからも、「行く前と行った後で何が変わりましたか。」「どのようにお金を貯めたのですか。」など様々な質問が出ていました。
最後に村田先生から、無限の可能性のある皆さんに、また会えることを楽しみにしています。というお言葉を頂きました。今日は年齢の近い先輩からの夢のあるお話をたっぷり聞かせていただき、生徒たちの心も日本を離れ海外に飛んでいるかもしれません。
2024年6月19日 by admin
附属小学校の5年生と田植え交流を行いました
○日 時 令和6年6月19日(水)3~4限
○場 所 本校農場
○対 象 2年生「地域資源活用」選択生
愛媛大学教育学部附属小学校の5年生95名が来校し、本校生徒と田植え交流を行いました。農業の授業で種もみから育てたうるち米品種「にこまる」の苗を1つずつ丁寧に田んぼに植えていきました。終始和やかな雰囲気で楽しく作業をすることができました。小学生にとって自然を楽しみつつ、食や農業のありがたみを学ぶ機会となっていれば幸いです。ちなみに、本校留学生のジェイク君は人生初の田植えだったみたいで、小学生と同じぐらい満喫していました。梅雨の合間の晴れ間で気温が上がり、熱中症等の心配もありましたが、無事作業を終えることができました。
愛媛大学教育学部附属小学校5年生との「持続可能な米作り」について考える協働授業は、今年で3年目となります。昨年度からは実際に本校農場で米作りを行っており、双方の学びを深め合っています。交流で使用する農場は、愛媛県特別栽培農産物認証(エコえひめ認証)に則り化学肥料・農薬を使用せずに栽培を行います。秋に小学生と一緒に稲刈り交流ができるよう、本校生徒たちが丹精込めて栽培管理を進めていきます。
2024年6月17日 by admin
産業社会と人間の授業を行いました
○日 時 令和6年6月17日(月) 6・7限目
○場 所 多目的教室
○対 象 第1学年
○講 師 愛媛大学農学部 治多伸介先生
「現代農学・農産業の重要性と発展性」というテーマで、1年生対象にご講演をいただきました。はじめに現代農学についてご説明いただき、現代農学は、生産性はもちろん、環境への配慮や持続性がより重要視されていることを理解することができました。現代農学に関連するキーワードとして、食料自給率の低下に伴う輸出入のバランス、水などの資源の枯渇、地球温暖化、高齢化社会がもたらす農業の後継者不足など、様々な角度からの諸問題について認識できました。また、愛媛大学農学部の紹介をしていただき、120年にわたる歴史や本校の前身である附属農業高校時代との関わりについても改めて知ることができました。そして後半には、「現代の農学・農産業の特徴」「農学・農産業の社会・地域における必要性・発展性」「愛媛大学農学部の特徴」という3つのテーマについてクラスごとにグループワークを実施しました。各クラスともPC等を使用しながら、活発に意見を出し合い、全体発表へと繋げました。本講義を踏まえ、農学に対する関心を深めるとともに、多くの課題意識を持つことができました。
2024年6月15日 by admin
オーストラリアとオンライン交流をしました
◯日 時 令和6年6月15日(土)
◯対 象 英語部
◯場 所 ワークショッププレゼンテーションルーム
今日の英語部は、交流を続けているオーストラリア在住のパトリックさんとオンライン交流をしました。「オーストラリアの動物と花を調べて1分間スピーチをする」課題をいただき、15人がそれぞれ発表しました。コアラやカンガルー以外の動物も知ることができ、自然あふれるオーストラリアの様子を学ぶことができました。これからオーストラリアは、冬になります。次の交流では、南半球の冬についても話していただきたいと思います。
2024年6月14日 by admin
グローバル・スタディーズⅡを行いました
〇日 時 令和6年6月14日(金)5・6限
〇場 所 大講義室
〇対 象 第3学年(GSⅡ 選択生)
〇講 師 岡山理科大学 木村 光宏 先生
本日のグローバルスタディーズⅡは、岡山理科大学の木村光宏先生による講義でした。「国際ボランティアとSDGs」というタイトルで、前半は、生徒が住む町の紹介をお互いに英語で行ったり、先生のJICA海外協力隊でのボランティア経験について講義を聞いたりしました。後半は「自分たちがJICA海外協力隊に参加するなら」というテーマで、希望する職種、ボランディアに行きたい国やその国の課題、そこで自分がやりたいことなどを調べ発表しました。また「JICA海外協力隊ボランティアとSDGs」というテーマでディスカッションを行いました。生徒は、現在の自分にできることは何か、自分自身の経験を今後どのように積み上げていくのかを考えたり、国際ボランティアがどのようにSDGsとつながっているのかを学ぶことができました。
2024年6月13日 by admin
1学期期末考査に向けた勉強会を行いました
〇日 時 令和6年6月13日(木)
〇場 所 ワークショッププレゼンテーションルーム
ホームルームの時間を利用して、1学期期末考査に向けた勉強会を開催しました。クラス全員を4人グループに分け、各グループが担当科目についてのテスト対策プリントを作成しました。グループが作成したプリントはクラス内で共有され、皆で各科目の重要ポイントを確認しました。この勉強会を通じて、協力し合いながら学びを深め、期末考査に向けた準備を整えることができました。
2024年6月12日 by admin
グローバル・スタディーズⅠを行いました
〇日 時 令和6年6月12日(水)6, 7時間目
〇場 所 大講義室
〇対 象 第2学年
〇講 師 愛媛大学教育学生支援機構 村田晋也先生
本日のグローバル・スタディーズⅠの授業では、愛媛大学の教育・学生支援機構から村田晋也先生をお招きし、キャリアガイダンスを実施していただきました。3回目となった今回は、「聴くこと」に重点を置いた内容でした。初めに聴き手側のマナー、能動的な聴き方と批判的な聴き方について教えていただきました。その後、大学生を招いてのトークライブが開催されました。トークライブの前に、今回のトークライブを聴くにあたっての聴き手としての目標を各自で設定しました。トークライブでは、留学についてのお話を聴くことができました。その後の質疑応答では、話し手から留学中の出来事や英語学習、スライドづくりのコツなど様々な話を引き出すことができました。また、村田先生からは学生時代の友人関係の大切さ、人間関係は資産であるという言葉や、型を身に付けてこそオリジナリティが生まれるなどのお話をしていただきました。最後に、聴き手としての目標をどのくらい達成できたか振り返りました。実践的で大変勉強になると同時に、とても楽しい授業でした。次回も大学生のトークライブがあります。新たな目標を立て、聴くことについて学んでいきたいです。
2024年6月10日 by admin
田植えを行いました
○日 時 令和6年6月10日(月)5~7限
○場 所 本校農場
○対 象 第1学年
本校の農場で、1年生を対象とした田植え実習が行われました。農業科の先生からの概要説明を受けた後、農場へ移動し、一斉に田植えを始めました。泥の感触を楽しみながら、一つ一つの苗を丁寧に植えることができました。
この日は本校の教職員や教育実習生も参加し、和やかな雰囲気の中で作業が進みました。雨が心配されましたが、天候にも恵まれ、程よい曇り空のもと、作業を終えることができました。田植えを通じて、食の大切さを実感し、自然とのつながりを深める貴重な経験をしました。
2024年6月9日 by admin
陸上競技ミライアスリート交流記録会に出場しました
○日 時 令和6年6月9日(日)
○場 所 愛媛県総合運動公園陸上競技場
○対 象 陸上競技部員
陸上競技部員(1年2名、2年1名、3年1名)が出場、また運営で参加しました。出場競技は男子400 m、男子100 m、男子200 m、女子走り幅跳びの4種目でした。雨のなかの競技ではありましたが、練習の成果を出し切ることが出来ました。
2024年6月9日 by admin
理科部員が農家の皆さん約50名を前に、絶滅危惧種の調査結果や地域の今後について説明しました
〇日 時 令和6年6月9日(日)
〇場 所 県内山間部の集会所
〇対 象 理科部1年生、地域住民、行政関係者、研究者など
理科部では絶滅危惧種マツカサガイの保全活動を続けています。この日は、今年度入学・入部したうち、この保全活動を引き継いでくれる1年生部員が、マツカサガイが生息する地域の農家さんの会合に参加しました。現地での2ヶ月の調査結果が出そろったため、その説明や将来の可能性などについて話すためです。地域の今後に大きく影響する内容でしたから、皆さん非常に熱心に聞いてくれました。地域の今後を左右するこの会合には、地域の方々だけでなく、行政関係者、研究者など、様々な人が集まって、知恵を出し合いました。予算、人にとっての利便性、防災対策、法、経済、期限、少子高齢化、環境、持続性・・・と、合意形成は非常に難しく、タイムリミットまでに会合はまだ続きます。より良い選択、納得をするためには、確かなデータと解釈が欠かせません。県の保護事業の一端を担うのは大変ですが、地域と環境のために、理科部の活躍が期待されています。