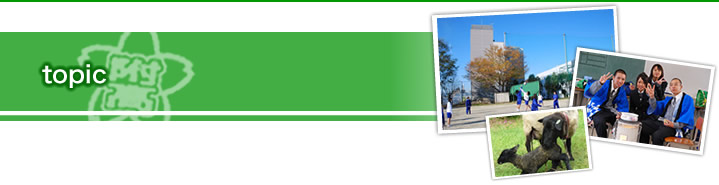
2025年7月29日 by admin
学校見学会で校内販売を行いました
〇日 時 令和7年7月28日(月)、29日(火)
〇場 所 本校1・2棟間の通路
〇対 象 農業クラブ本部役員
農業クラブ本部役員を中心に、学校見学会で校内販売を行いました。柑橘類のジュースやタマネギに加え、当日収穫した卵とミニトマトも販売しました。2日間を通して準備していた販売商品は、すべて完売となりました。お買い上げいただいた皆様ありがとうございました。生徒たちは、商品の見せ方や声かけに工夫を凝らし、充実した販売実習となったようです。これからも収穫したものは随時、2棟1階にて校内販売を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年7月29日 by admin
カマイルカの骨を提供していただきました
○日 時 令和7年7月29日(火)
○場 所 愛媛大学附属高校
○対 象 理科部
愛媛大学大学院医学系研究科の下川哲哉先生より、カマイルカの全身骨格やライオンの頭蓋骨などをご提供いただきました。カマイルカの全身骨格については、骨格標本の完成に向けた作業が途中まで行われており、残りの作業を本校で行います。また、ライオンの頭蓋骨などについては、それぞれの特徴や他の動物との違いを下川先生に詳しくご説明いただきました。このような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。
2025年7月28日 by admin
理科部が県代表として全国高等学校総合文化祭自然科学部門に出場しました
○日 時 令和7年7月26~28日
○場 所 香川大学、高松中央高等学校
○対 象 理科部 3年 天野颯人
香川大学で行われた「かがわ総文2025」全国高等学校総合文化祭自然科学部門の研究発表会に、理科部で3年間研究に取り組んだ天野颯人さんが参加しました。昨年度、愛媛県の自然科学部門生物分野で最優秀賞に選ばれ、県代表としての参加です。2日間に渡って、各県の代表者が研究発表を行い、活発な質疑応答を行いました。2日目には秋篠宮皇嗣同妃両殿下が研究発表を視察され、貴重な経験になりました。3日目は記念講演の他、香川大学医学部での巡検研修で、ブタの肺を用いた人工呼吸、電気メスやマニピュレーター操作などの医療体験を行い、学び多い3日間となりました。
2025年7月26日 by admin
応用物理・物理系学会で発表しました
○日 時 令和7年7月26日(土)
○場 所 岡山大学 津島キャンパス
○対 象 理科部
理科部員が「2025年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 ジュニアセッション」において、「はんぎり競漕における水の流れの特徴」という題目で研究発表を行いました。一般講演の参加者も交えた口頭発表では、研究内容の改善点や今後の展開について、大学の先生方から貴重な助言をいただきました。また、高校生によるポスターセッションでは、県外の高校生と活発に意見交換を行い、互いの研究をさらに深める機会となりました。
2025年7月26日 by admin
全国総文祭報告(愛媛県高等学校合同オーケストラ)
○日 時 令和7年7月26日(土)
○場 所 ハイスタッフホール(香川県観音寺市)
○対 象 本校生徒有志2名
愛媛県代表の合同オーケストラに本校から2名の生徒が参加しました!昨年から練習していたバレエ音楽「エスタンシア」を振り付けつきで演奏しました。高校から楽器を始めた人、オーケストラのリーダーに選出された人、楽器の経験はそれぞれでしたが、他の学校の人たちとうまくコミュニケーションをとって、最高の演奏を届けることができました!今年度の愛媛県高等学校総合文化祭も合同オーケストラで出演いたします。応援よろしくお願いします!
2025年7月25日 by admin
「戦後80年プロジェクト」インタビュー動画の編集を行いました
〇日 時 令和7年7月23日(水)~25日(金)
〇場 所 テレビ愛媛
「愛附生が聞く戦後80年プロジェクト」の戦争体験者に対するインタビューが全班終了し、7月23日からテレビ愛媛の編集室で班別に動画の編集を行いました。各班1時間以上に及ぶ動画を10分前後にするため、流れを考え、動画を前後入れ替えたり、字幕スーパーを差し込んだり、話題が変わる部分にはナレーションを入れるなど、テレビ局の機器を使用し2時間ほど編集作業を行いました。
完成した動画は今後、テレビ愛媛の公式ホームページにアップされますので、ぜひご視聴ください。
2025年7月24日 by admin
令和7年度愛媛県高等学校国際教育リーダー研修会に参加しました
○日 時 令和7年7月24日(木)
○場 所 IYOみらい館
○対 象 有志生徒
令和7年度愛媛県高等学校国際教育リーダー研修会に有志5名が参加しました。今年度は、愛媛県内のさまざまな高校から集まった、学年の異なる有志がグループを組み、貿易ゲームに挑戦しました。貿易ゲームは、紙を「資源」、ハサミや定規などを「道具」に見立てて製品を作り、それを使って他のグループと貿易しながら、どれだけ多くの富を築けるかを競う参加型のワークショップです。附属の生徒の皆さんは、ドイツからの留学生を含む初対面のメンバーに囲まれ、緊張した面持ちでスタートしました。しかし、世界の挨拶を使ったアイスブレイクや、世界の現状に関するクイズに挑戦するうちに、ほかの参加者と打ち解け、次第に笑顔でワークショップに参加することができました。ものを売り買いしたり、他のグループと交渉したりして貿易を疑似体験し、世界の現状や経済について学ぶ良い機会となりました。
2025年7月19日 by admin
松山市との共催で理科実験教室を開催しました
〇日 時 令和7年7月19日(土)
〇場 所 生物室
〇対 象 小学4年生から6年生の女子児童およびその保護者
本校の生物室で「親子で学ぼう ~理科好き女子は愛媛大学附属高に集合~」と題した理科実験教室を開催しました。本講座は、松山市男女共同参画推進センター・COMSと愛媛大学附属高等学校理科部の共催で行われ、講師は理科部の生徒が務めました。
対象は小学4年生から6年生の女子児童およびその保護者で、当日は22組の親子にご参加いただきました。参加者には、理科実験を通して実際に理系を志している高校生と交流し、進路選択のきっかけとなるような体験をしていただきました。
講座では、表面張力に関する実験と光に関する実験を行いました。表面張力の実験では、条件を変えるとどのように結果が変わるのかについて、高校生と一緒に考えながら観察する場面も見られました。光に関する実験では、散乱や偏光、干渉などさまざまな光の現象を観察してもらいました。
講座終了後には、附属高校で飼育しているヒツジや水槽の見学も行いました。生き物とふれあうことで、生物分野への関心もより深めることができたのではないかと思います。
今回の講座を通じて、理科のさまざまな現象に触れるだけでなく、愛媛大学附属高校についても知っていただく良い機会となりました。ご参加いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。
2025年7月18日 by admin
七夕茶会を開催しました
〇日 時 令和7年7月18日(金)12:30~15:00
〇場 所 3棟3階作法室
茶道部主催の七夕茶会では、総勢20名の部員が1学期のお稽古の成果を披露しました。今回は、七夕、うちわ、くず餅の3種類のお菓子を用意して、お客様をお迎えしました。女子部員は全員が浴衣姿で、夏を演出しました。終業式後の午後に実施しているため、例年は参加人数がそれほど多くありませんが、今年は先生方を含め、総勢45名のお客様にお越しいただきました。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。そして、3年生にとっては、この茶会が3年間の集大成となりました。今まで本当にありがとうございました。お疲れさまでした。
2025年7月18日 by admin
1学期終業式を行いました
〇日 時 令和7年7月18日(金)
〇場 所 各HR教室 (オンライン形式)
〇対 象 全校生徒
終業式に先立ち、各種表彰伝達とインターハイ壮行会が行われました。
終業式では、1学期の学校行事や部活動における生徒の頑張りについて、校長先生からお話がありました。続いて、7月末で退職される木村先生からご挨拶をいただきました。ある人物の言葉を引用されながら、思いやりや優しさを持って人と接することの大切さについて、お話しいただきました。木村先生には、これまで本校の教育活動を温かく支えていただき、本当にありがとうございました。
最後に、生徒課長の先生から夏休み中の生活に関する諸注意がありました。夏の時期は、海や川など水辺で過ごす機会が増えます。それに伴い水難事故も多く発生しています。命を守るための行動や心構えについて再確認し、安全と健康に気を付けながら、充実した夏休みを過ごしましょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||