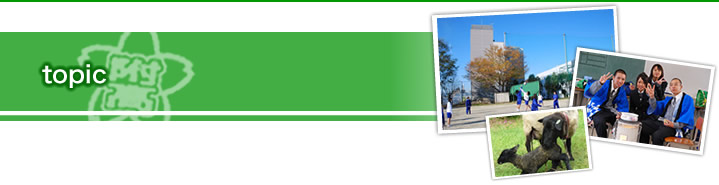
2022年2月4日 by admin
令和3年度 愛媛大学附属高等学校教育研究会 国語科の部 申し込みについて
2022年2月4日
令和4年3月8日(火)に「令和3年度 愛媛大学附属高等学校教育研究大会 国語科の部」を開催いたします。毎日の教室で実践に取り組まれている先生方や、大学で教科教育を深められている研究者、学生の皆さんなど、それぞれのお立場からご意見をいただき、学びあう会になることを目指しております。
是非、ご参加ください。
申し込み方法:
①下記の「申し込みフォーム」より必要事項を入力
②「申し込みフォーム」の一番下にある「送信」をクリックする
③申し込み完了
○「令和3年度 愛媛大学附属高等学校教育研究大会 国語科の部」
2022年2月2日 by admin
グローバル・スタディーズⅠを行いました
○日 時 令和4年2月2日 水曜日6・7限
○場 所 HR教室(オンライン)
○対 象 2年生全員
○講 師 愛媛大学アジア古代産業考古学研究センター 村上 恭通 先生
愛媛大学アジア古代産業考古学研究センターの村上恭通先生から、「発掘が解明する瀬戸内海の歴史―縄文時代から中世まで―」をテーマに、考古学の観点から瀬戸内海の歴史について遠隔による講義を受けました。しまなみ海道にうかぶ弓削島と佐島を例に挙げ、縄文時代から中世までの発掘調査の結果と考察が紹介されました。弓削島荘は塩の荘園としても知られていますが、実際に中世の地層からは揚浜式塩田の跡が見つかっており、その重要性を再確認しました。今治市にある奈良時代の遺跡からは製鉄炉が発見され、四国初、四国唯一の例となっています。これは、当時大陸から入手しにくくなっていた鉄の原料が豊富で、森林資源や環境も整っている今治に、国家事業の一環として導入されたためと考えられます。
また、宮ノ浦遺跡の地層については、植物が繁茂して生物が増え、それらの腐敗により有機化が進みクロスナ層を形成したとし、宮ノ浦遺跡が存在した古墳時代開始期は温暖期であったことが示されました。クロスナ層からは製塩土器も出土しています。破壊して中の塩を取り出すため原型をとどめているものは少ないですが、人が生活していた痕跡がうかがえるものです。最下層の縄文時代の地層からは打製石鏃や中四国内ではあまり例のない撚糸文土器が出土しました。この当時は瀬戸内海は存在しておらず、人々は海を知らなかったことが明らかとなりました。まだ知られていない伊予の歴史が、発掘によって次々と解明されていることを、実例をもって示していただきました。
2022年2月1日 by admin
デジタルコンテストホームページ部門において愛媛県代表に選出されました
〇日 時 令和4年1月20日(木)
〇対 象 愛媛大学附属高等学校
慶應義塾大学SFC研究所アグリプラットフォームコンソーシアム主催の「全国農業高校・農業大学校デジタルコンテストホームページ部門」におきまして、一次審査の結果特に優秀と認められ、本校が愛媛県代表に選ばれました。今年度で3回目の選出となります。一次審査において代表校に選出された高校を対象に、今後本審査が行われます。
2022年1月31日 by admin
SDGs伊豫学の授業を行いました
〇日 時 令和4年1月31日(月)6・7限
〇場 所 各HR教室(遠隔)
〇対 象 1年生
大学院農学研究科 八丈野孝准教授による授業が行われました。はじめに「研究者(理系)になるために必要なこと」ということで研究者をめざす高校生に8つの項目が紹介されました。
また、柑橘全般に一番厄介な病気「カンキツかいよう病」、柑橘が色づかない「カンキツグリーニング病」、バナナの「パナマ病」…など様々な作物の病気のお話がありました。世界的に大問題になっていることでも、輸出に頼っている日本では報道されていない情報がたくさんあることに皆驚いていました。
「ジャガイモ疫病は人類の歴史を変えた!?」という話では、ジャガイモに病気が流行り1845年からのアイルランド大飢饉で100万人が餓死し、200万人がアメリカ・イギリス・カナダ・オーストリアに移住せざるをえなくなったという話もあり、作物の病気が人の生命・生活に大きな影響を及ぼすということを改めて確認する機会となりました。
2022年1月26日 by admin
| 必要書類 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 1 | 証明書交付申請書 証明書交付申請書の記入例 |
窓口にも証明書交付申請書を用意しています。 |
| 2 | 本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれか1つ ※代理人による申請の場合は申請者の本人確認書類の写しを提出してください。 ※マイナンバーカードの使用はご遠慮ください。 |
| 1 | 切手の貼った返信用角2封筒 (宛先記入済み) |
※郵送料金については下の<郵送料金の目安>をご一読ください。 |
| 1 | 委任状 委任状の記入例 |
申請者本人が記入、署名、捺印したもの ※コピー不可 |
| 2 | 代理人の本人確認書類の写し | 運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれか1つ ※マイナンバーカードの使用はご遠慮ください。 |
| 証明書 | 厳封( 有 ・ 無 ) | 発行日数 |
|---|---|---|
| 卒業証明書 | 無 | 和文 翌々日/英文 翌々日~1週間程度 |
| 成績証明書 | 有 | 翌々日~1週間程度 |
| 調査書 | 有 | 翌々日~1週間程度 |
ただし、土日祝日、お盆、年末年始をはさむ場合、必要書類の不備や記入漏れ及び確認事項がある場合はさらに日数がかかりますのでご注意ください。※即日発行はできませんので時間に余裕を持って申請してください。
ご提供いただいた個人情報は、証明書発行に関する業務に利用します。
取得した個人情報は、前記の目的以外に利用することはなく、また、公表することはありません。
ご提供いただいた個人情報は、証明書発行に関する業務に利用します。
<郵送申請に必要な書類の確認事項>
<卒業後、改姓または改名された方へ>
愛媛大学附属高等学校では、在学時の氏名で証明書を発行しています。
改姓または改名後の氏名では発行できませんので、ご了承ください。
また、改姓または改名の確認として、本人確認書類とは別に、改姓または改名されたことが確認できる書類を提出していただくようお願いします。
【改姓または改名されたことが分かる公的書類】 氏名変更が記載された運転免許証の裏面(※押印されたもの)、年金手帳の氏名変更欄(コピー可)、パスポートの改姓欄と氏名欄(旧姓と現姓を確認するため両方必要。コピー可)、戸籍抄本(コピー可)
不備などがあれば、ご連絡します。連絡がつかない場合は、証明書の発行が遅れますのでご注意ください。
| 証明書枚数 | 定形外郵便( 240mm×332mm ) | 追加料金(別途必要) |
| 1枚~3枚 4枚~6枚 |
140円 180円 |
<特定記録> +210円 <速達> +300円 <簡易書留> +350円 |
※証明書1枚(A4サイズ)の重さ…約5g、証明書厳封用の封筒 長3(120mm×235mm)
※返信用封筒:角2封筒(240mm×332mm)に宛名(本人に限る)を記入し、切手を貼付してください。
宛先 〒790-8566 愛媛県松山市樽味3丁目2番40号 愛媛大学附属高等学校 事務室
封筒表面に「証明書交付申請書在中」と記載ください。
2022年1月26日 by admin
グローバル・スタディーズⅠを行いました
○日 時 令和4年1月26日 水曜日 6・7限
○場 所 HR教室(オンライン)
○対 象 2年生全員
○講 師 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 岩田久人先生
「野生動物の健康を評価する環境毒性学」というテーマで講義をしていただきました。冒頭に、愛媛大学沿岸環境科学研究拠点(LaMer)の歩みと活動内容について説明があり、講義の本題に入りました。
まず、「リスク」というのは「ある」か「ない」かではなく、連続的な数字で表されること、化学の世界に置き換えて考えると曝露量と有害性を把握する必要があることを学びました。そして、化学物質のリスクに関わる要因には、環境要因と遺伝要因があり、化学物質のリスク評価には遺伝要因の理解が不可欠であることを講義していただきました。
講義の後半では、ロシアのバイカル湖に生息するバイカルアザラシの大量死の原因となった環境汚染物質(=ダイオキシン類)について学びました。岩田先生ご自身が研究を重ねるうちに、ダイオキシン類の毒性発現メカニズムが解明され、バイカルアザラシがダイオキシン類に対して感受性が高く、高いリスクに曝されていたことが分かりました。産業の発達と共に我々人間の生活は豊かになりましたが、生物多様性保全の観点からも野生動物への影響を正しく評価し、行動することの重要性を学ぶことができました。
2022年1月26日 by admin
SDGs伊豫学の授業を行いました
○日 時 令和4年1月26日(水)5~6限目
○場 所 各HR教室(リモートによる実施)
○対 象 1年生120名
〇講 師 愛媛大学法文学部 小田敬美 先生
本日のSDGs伊豫学のテーマは「ブラックバイトに遭わないために 〜明るい職場×やりがいのある仕事で築く私の未来〜」でした。
まず、本授業に関連するSDGsが「8 働きがいも 経済成長も」、「16 平和と公正をすべての人に」であることを確認し、雇用に関する憲法や国際法、契約について学びました。なかでも、最近身近になっている食事配達サービスやフリマサービスなどは、労働法や消費者法が適用されないことを知ることができました。
そして、相談事例をもとにブラックバイトに関するQ & A について考えました。最後に、これまでに学んだ労働契約や就業規則などを踏まえて、高校卒業後の働き方について考えることができました。
2022年1月24日 by admin
SDGs伊豫学の授業を行いました
○日 時 令和4年1月24日(月)6・7限
○場 所 各教室(オンライン授業)
○対 象 1学年全員
○講 師 愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンター 廣岡 昌史 先生
本日は愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンターの廣岡昌史先生より愛媛の医療と福祉についての講義をしていただきました。始めに医学部について紹介をしていただき、パンフレットやHPだけでは分からない医学部の様子を知ることができました。また、仕事もプライベートも充実させている廣岡先生ご自身のことについてもお話いただき、医学部に進んだからといっても勉強だけじゃない、と感じました。
愛媛県については、高齢化が進んでおり、南予や、今治の島嶼部などでかなり高齢者の割合が高くなっている中、松山市以外の地域では医師の数が全国平均を下回っており、少し前には八幡浜市内の産婦人科がなくなったというニュースもあったということです。
現在、愛媛県でも、ケアマネージャーが司令塔となり、地域包括ケアシステムのもと高齢者の生活をサポートしていますが、withコロナ時代の問題点2つ、「入院しているコロナウィルス感染患者とその家族の面会をどのようにして可能にするか」、「自宅での治療を希望する感染者への対応をどうするか」という課題について考えました。ちなみに、人類がワクチンで唯一撲滅できたウィルスは天然痘のみで、しかもワクチンができてから撲滅までには180年もかかったそうです。
「ゼロコロナ」ではなく、「withコロナ」の今、問題解決に向け活発に意見交換をすることができました。廣岡先生からは、何が答えということはないが、Alexaなどのような簡単に使えるツールを普及していくこと、自宅で看護をする場合は感染対策を高める必要があるとアドバイスをいただきました。
2022年1月24日 by admin
◎令和4年度 連絡入学・推薦入学試験合格者受験番号一覧 (PDF)はこちら
なお、ホームページ上の発表は参考として閲覧の上、必ず「合格結果の通知書」により確認してください。
合格者については、入学手続き関係書類を中学校長宛に送付しました。
≪連絡入学・推薦入学試験得点等の口頭による開示請求について≫
学力検査の得点については、国立大学法人愛媛大学保有個人情報開示等に関する取扱規程に基づき、
口頭による開示請求をすることができます。
〇期 間 令和4年1月24日(月)~2月22日(火)
〇時 間 月曜日から金曜日までの9時から16時30分まで(国民の休日は除く)
〇場 所 愛媛大学附属高等学校 事務室
〇対 象 受験者本人のみ(電話、はがき等による請求はできない)
〇確 認 本人と確認できる書類(受験票等)が必要
〇開示内容 (連絡・推薦入試)基礎テスト・小論文の得点、並びに調査書の評定の合計
2022年1月21日 by admin
令和4年1月21日
受験生・保護者の皆様・各中学校の先生
愛媛大学附属高等学校
校 長 隅田 学
令和4年度 一般入試における新型コロナウィルス感染者の
濃厚接触者と判断された場合の対応について
時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。本校の教育並びに教育理念につきまして、御理解をいただき感謝申し上げます。
さて、2月8日(火)・9日(水)に実施されます令和4年度一般入試におきまして、受験生本人が新型コロナウィルス感染者の濃厚接触者に該当すると判断された場合は、速やかに中学校を通じて本校に御連絡をお願いいたします。
「新型コロナウィルス感染者との濃厚接触者申出用紙」をダウンロードし、必要事項を記入し、本校にメール、FAXなどで提出をお願いいたします。
愛媛大学附属高等学校
〒790-8566 愛媛県松山市樽味3丁目2番40号
TEL:089-946-9911 FAX:089-977-8458
Mail:aifu@hi.ehime-u.ac.jp
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||