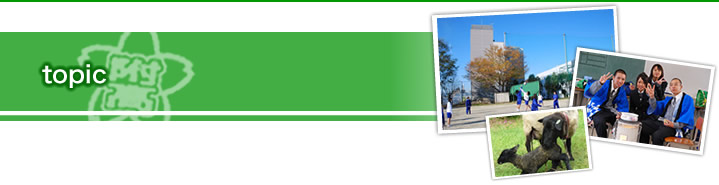
2022年7月4日 by admin
SDGs伊豫学の授業を行いました
○日 時 令和4年7月4日(月)6・7限
○場 所 各HR教室(対面及びZoomによる講義及び個別指導)
○対 象 第1学年
○講 師 マイナビ 森田 えり 先生
森田先生に「探究の進め方」というテーマで講義をしていただきました。探究活動とは、「①自分で課題を設定するもの②自分で問いを立てるもの③自分が主体的に取り組むもの④テーマが与えられた調べ学習とは違うもの」ということでした。そして、「課題設定では、自分が疑問に思っていることを追究すること。その時、大事にしてほしいのは、自分の感情が動くこと、感情が動く疑問を見つけ出すこと。」と、「感情」の大切さを強調されました。たとえば、「むかし家族で行った海。きれいだった。楽しかった。最近汚れてきた・・・?」という自分の感情を思い出した。その海を調べていくと、「清掃団体があること」、「団体数は意外と多いこと」、しかし、「汚れていること」が分かった。「自分も何かできないかと」思うようになった。ここで、「海」、「きれい」、「汚い」という自分の感情とSDGs14番「海の豊かさを守ろう」を掛け合わせて考えてみる。すると、大人、学生、子どもが自発的に「参加したい」と思えるような清掃・ボランティア活動はどんなプロモーションが必要なのかといった「問い」が生まれてくる。自分の感情が動く疑問を見つけることができる。このような例を3つ挙げて分かりやすく説明をしていただきました。さらに、「探究活動を通して、また、学校生活を通して、皆さんに得てほしいことが2つある。」と言われました。それは、「考え方は1つではない」ということと「見えない選択肢もある」という2つで、「これは、将来の進路選択にもつながる考え方でもある」ということでした。「自分が目指す『なりたい自分』を想像しながら、『自分らしい生き方』、『自分らしい働き方』を、探究活動を通して、学校生活を通して、これから修得していってほしい。」と熱く語っていただきました。
後半は、ワークシートで、テーマ(課題)の設定やその設定理由を考えました。森田先生に各クラス回っていただき、個別に指導・助言もしていただき、生徒一人一人は、自分なりのテーマの設定ができていました。
森田先生、本日は、高校生1年生にとっても、教員にとっても、分かりやすく、実になるお話をたくさんしていただき、大変にありがとうございました。
2022年7月1日 by admin
グローバル・スタディーズⅡを行いました
○日 時 令和4年7月1日(金)5・6限
○場 所 大講義室
○講 師 アメリカ ベラ・ビスタ高校 森山ななこ先生
○対 象 第3学年(GSⅡ選択生68名)
「グローバル・スタディーズⅡ」第10回目の授業では、アメリカ、ベラ・ビスタ高校から森山なな子先生をお迎えし、「世界とのつながりを考える―アメリカでの日本語教育、インドでのボランティア経験をもとに―」というテーマでお話をしていただきました。対面で講義をしていただくのは今年度初めてで生徒も大変楽しみにしていました。森山先生はベラ・ビスタ高校で日本語を教えておられます。MentimeterやKahoot!を用いて、クイズなどを交えながら、ベラ・ビスタ高校の紹介をして下さったり、インドでのボランティア活動を通して経験した文化の違いについて、お話してくださいました。「アメリカの高校で日本語を教えるとしたら、どんな授業を行うか」「JICAボランティアにどんな種類があるか、自分に合う職種を探す」の課題が出され、生徒たちはその場でGoogleFormsに書き込む形で答えました。生徒の感想には「言葉を学ぶことを通して、その土地に根付いた文化やそこに住む人々のことを受け入れられるようになりたい。好きなこと、得意なことを伸ばすことによって、誰かの手助けができるようになりたい」というものがありました。森山先生の自分の好きなことにどんどん挑戦していく生き方に勇気づけられ、感銘を受けた生徒も多かったようです。参加型の講義に生き生きと取り組む姿がとても印象的でした。
2022年6月30日 by admin
ふれあいの道を行いました
○日 時 令和4年6月30日(木)
○場 所 学校周辺道路
○対 象 全学年希望者
ふれあいの道を行いました。愛大附属の有志、約100名が集い、学校周辺道路などの清掃活動を行いました。みんなテスト終了後の猛暑の中、汗をいっぱい流しながら時間の限り活動してくれました。清掃後のきれいになった場所を見て、みんなで喜びました。次回は2学期末、頑張ります!!
2022年6月30日 by admin
野球部壮行会を行いました
○日 時 令和4年6月30日(木)
○場 所 運動場
○対 象 全学年
野球部壮行会を行いました。愛媛県大会では日頃の練習の成果を十分に発揮し、1試合1試合を大切に戦い抜いて欲しいと思います。全校生徒で応援しています!
1回戦は7/10(日)・10時~今治球場で今治北高校大三島分校と対戦します!!
2022年6月24日 by admin
インターハイ35日前カウントダウン活動を行いました
○日 時 令和4年6月24日(金)
○場 所 羊小屋前
○対 象 全学年
愛媛県でインターハイが開催されるまで、残り35日となりました。インターハイ開催期間中は私たちもJR松山駅で総合案内活動を行ったり、愛媛県総合運動公園でおもてなし活動を行ったりする予定です。みなさんもインターハイを盛り上げ、ぜひ一緒に来県者をおもてなししましょう!!
松山・大洲・喜多地区。次は、大洲高校です!!
2022年6月23日 by admin
インターハイ四国4県一斉PR活動を行いました
○日 時 令和4年6月23日(木)
○場 所 各教室
○対 象 全学年
インターハイ四国4県一斉PR活動を行いました。令和4年度のインターハイは四国4県と和歌山県の計5県で開催されます。愛媛県でも5市で8競技が開催され、松山市では体操、ハンドボール、柔道が開催されます。また、インターハイに本校からも自転車競技で竹内奨吾さんが出場します。年に1回の大会で、選手のみなさんが思いっきり充実した思い出ができるよう、応援しましょう!!
2022年6月20日 by admin
SDGs伊豫学の授業を行いました
○日 時 令和4年6月20日(月)
○場 所 各教室(オンライン授業)
○対 象 1学年全員
○講 師 愛媛大学宇宙進化研究センター 清水徹先生
愛媛大学宇宙進化研究センターの清水徹先生に、宇宙への招待「宇宙天気予報」というテーマで講義をしていただきました。宇宙進化研究センターには大規模構造進化部門、ブラックホール進化研究部門、宇宙プラズマ環境研究部門がありますが、どれも四国では愛媛大学でしか学べない内容です。講義では、非常に美しい画像を豊富に用いて、分かりやすく説明していただきました。前半は、私たちが毎日見ている太陽や、太陽風について教えていただきました。私たちが見る太陽は、8分前の太陽の姿で、私たちの地球は太陽の活動の影響を強く受けています。後半は先生のご専門の宇宙天気予報の研究についてのお話でした。私たちの地球環境は、絶妙なバランスの上に成り立っています。広大な宇宙において、奇跡的に私たちが生活できるこの環境、今しか無いこの時代、できることに精一杯取り組んでいきたいものです。
2022年6月17日 by admin
グローバル・スタディーズⅡを行いました
○日 時 令和4年6月17日(金)
○場 所 大講義室・多目的教室
○対 象 第3学年(GSⅡ選択生68名)
「グローバル・スタディーズⅡ」第9回目の授業では、オンラインとなりましたが、フィリピン大学のロリーナ先生をお迎えし、「ネット上のデマに関するフィリピン人の脆弱性への理解」という演題で講義をいただきました。フィリピン人がデマに弱い理由を、歴史とデータを丁寧に紐解きながら解説いただきました。SNSの利用者が多いフィリピンが抱える課題は、SNSが身近な日本も同様であると感じた生徒も多かったようで、質疑応答では多くの生徒が挙手しロリーナ先生に質問を投げかけていました。愛媛大学からは、フィリピン事情に精通されている菅谷成子先生、本校の前校長 隅田学先生もご参加いただき、賑わいを見せました。すべて英語での講義でしたが、3年生は充実した様子で授業に臨んでいました。
次回は、アメリカ ベラビスタ高校の森山なな子先生が来校され講義されます。非常に楽しみです。
2022年6月16日 by admin
理科部が第17回高校環境化学賞で最優秀賞(松居記念賞)と奨励賞を受賞しました
〇日 時 令和4年6月16日(木)
〇場 所 富山県国際会議場
〇対 象 理科部(相原光希・渡壁希美、中村柑南・渡壁咲希・高尾実里、村上陽向・近藤百々花・松本麗)
環境化学物質3学会の合同大会が4日間にわたって富山県国際会議場で開催され、その中で高校環境化学賞という、高校生対象の科学研究コンテストが開催されました。これは、全国からエントリーのあった科学研究論文を、学会賞受賞研究者らが査読・得点化して上位3作品を選び、その3チームがポスター発表による最終審査で最優秀賞(=松居記念賞)か優秀賞かを競うものです。今年度はその3校に加え、計11校が富山でポスター発表を行いました。発表当日は、発表開始1時間以上前~発表1時間後まで、研究者による質問や議論が絶え間なく続く白熱したものとなりました。最終審査をうけた理科部酢酸菌セルロース研究班の相原さん、渡壁さんが最優秀賞(松居記念賞)を受賞しました。また、マツカサガイ保全研究班、プラガールズが奨励賞を受賞しました。
2022年6月16日 by admin
第4回Eカフェを行いました
○日 時 令和4年6月16日(木)
○場 所 リサーチプロジェクトルーム、アクティブラーニングルーム、教員研修研究室
○対 象 全校生徒
第4回「Eカフェ」は、インドネシア、ミャンマーからの留学生が対面で参加し、本校英語教諭のクラスも作りました。今回の話題は「母国の紹介」です。インドネシアでは外食文化が盛んで、街には屋台がたくさんあり「ナシゴレン」と呼ばれるチャーハンのような食べ物が人気だそうです。また、ミャンマーの学校では、日本のように一人ずつ机と椅子が分かれおらず、長椅子・長机で授業を受けると話していました。本校教諭は、イングランドやオーストラリアなどについて、気候や天気、英語のアクセントなど、日本人が知らないような部分に注目して教えてくれました。生徒は留学生に質問したり、逆に日本について紹介するなど楽しみながら時間を過ごしました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||