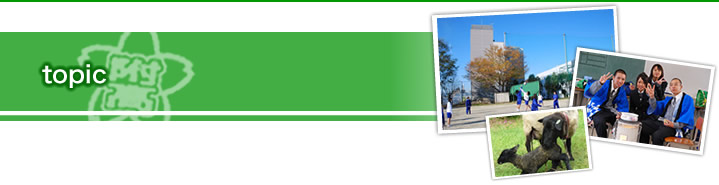
2023年4月11日 by admin
部活動紹介を行いました
〇日 時 令和5年4月11日(火)
〇場 所 体育館
〇対 象 第1学年
今年度入学した1年生を対象に部活動紹介を行いました。本校には、13の体育部と15の文化部があります。各部、編集した映像を見せたり、実演したりなど工夫を凝らして、紹介を行っていました。自分のやりたいことを見つけ、高校生活を楽しみましょう。
2023年4月10日 by admin
令和5年度入学式を挙行しました
〇日 時 令和5年4月10日(月)
〇場 所 体育館
〇対 象 全学年(2、3学年は遠隔)
やわらかな陽ざしと草木の香りが春の心地よさを伝えてくれる今日、晴天に恵まれ入学式を挙行しました。
123人の新入生の皆さんが、生徒・保護者・教員が作製した生花のコサージュを身に付け、入学を許可されました。吉村直道学校長、仁科弘重学長、PTA会長からの式辞・挨拶を聞く新入生の姿は晴れ晴れとして、頼もしくもありました。
引き続き行われた対面式では、新入生代表による挨拶と生徒会長による歓迎の挨拶がありました。
新入生の皆さん、皆さんが入学する今日という日を在校生・教職員一同心待ちにしていました。これからよろしくお願いします。
2023年4月10日 by admin
令和5年度新任式・始業式を行いました
〇日 時 令和5年4月10日(月)
〇場 所 各HR教室 (遠隔で実施)
〇対 象 2、3学年
始業式に先立ち行われた新任式では、新しく本校に赴任された4人の先生から生徒に向けた挨拶がありました。新しい先生との春の出会いは嬉しいですね。今後の授業や休み時間、行事でたくさん関わっていきましょう。
始業式では、吉村直道学校長より式辞がありました。生徒課長からは校則改定についてのお話もありました。
本校では3月にかわいい赤ちゃん羊も生まれています♪新しい先生、新しい友達、新しいルール、新しい1年生との出会いを大切に、今年1年も楽しんで過ごしていきましょう!
2023年4月10日 by admin
フィンランドから留学生が来ました
〇日 時 令和5年4月10日(月)
〇対 象 エスコラ・イーロくん
フィンランドから留学生(エスコラ・イーロくん)を迎え、附属高校の新学期がスタートしました。本日は留学初日でしたが、早速、クラスメートと仲良くなった様子です。授業、農業実習、学校行事、部活動などを通じて、いろいろな学年の生徒と交友が広がりそうです。来年2月までの約1年間の留学予定です。一緒に附属ライフを楽しみましょう。
2023年4月8日 by admin
理科部が愛媛県の環境保護保全団体を紹介する冊子に掲載され、エミフルMASAKIでの記念イベントにブース出展しました
〇日 時 3月下旬配布
〇場 所 県下の学校や公共施設
〇対 象 理科部、愛媛で環境保護に取り組む団体、愛媛県環境政策課
愛媛県で環境保全や自然保護活動に取り組む団体を紹介する冊子「EHIME ECOPRO GUIDE」が作成され、本校理科部によるマツカサガイ保全活動が掲載されました。完成を記念して、2/18にはエミフルMASAKIで記念イベント「エヒメエコプロショーケース」が開催され、本校理科部もブース出展しました。本校理科部は、県指定の唯一のタナゴ類とイシガイ類の保護施設であり、淡水性二枚貝マツカサガイの水槽飼育技術を持つ全国唯一の施設です。
2023年4月7日 by admin
入学式コサージ製作を行いました
〇日 時 令和5年4月7日(金)
〇場 所 環境ラーニングルームⅠ
〇対 象 2・3学年生徒・保護者の有志
入学式用のコサージ製作を行いました。材料の花は生徒が授業などで種から栽培したものを使用し、製作は2・3年生の有志や保護者の方々、先生方のご協力を得て行いました。今回もたくさんの思いが詰まったオリジナルのコサージが完成し、新入生の門出に花を添えることができたと思います。
2023年4月7日 by admin
マスク及び健康観察について
生徒及び教職員については、学校教育活動においてマスクの着用を求めないことを基本とします。ただし、登下校時に混雑した電車やバスを利用する場合などは、マスク着用を推奨します。咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うようにしてください。いつでも状況や場面に応じて、マスクが着用できるようにマスクを持参してください。
また、毎朝、健康観察を行ってください。登校前に検温と体調異常がないかどうかを確認してください。SHRで健康観察記録表に記入します。健康で充実した学校生活が送れるよう、みなさんのご協力をお願いします。
2023年3月28日 by admin
校則の改定について
昨今より学校を取り巻く社会環境や生徒の状況の変化に応じて、校則の見直しを行いました。これまでの経緯と改定した校則についてご連絡させていただきます。なお、改定した校則は、来年度令和5年4月1日から適用いたします。
実際に4月1日より運用し、うまくいかなかったり、新たな課題が見出されたりした場合は、生徒、保護者の皆様からの意見を取り入れ、柔軟に対応していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
~これまでの経緯~
(令和3年度)
0 10月:後期に改選された、当時2年生中心の生徒会より、校則改定の提案
(令和4年度)
0 4月:生徒会が、校則改定に向けての過程を検討
0 10月:生徒会が中心となり、全校生徒に有志の校則検討委員を募集
0 11月:各クラスで、校則検討委員が意見を吸い上げ、校則検討委員会を重ねて内容をまとめる
0 1月:その内容を踏まえて、教員の校則検討委員会にて検討
0 2月:職員会議において、内容確認、意見収集を行い修正
0 3月:生徒、教員合同の校則検討委員会にて意見交換し、さらに修正
0 0 PTA生活指導部会の方々から御意見をいただき修正
0 0 職員会議にて審議され承認
2023年3月27日 by admin
プラガールズの春休み遠征
〇日 時 令和5年3月21日(火)~23日(木)、27日(月)
〇対 象 プラガールズ 2年 村上陽向、近藤百々花
0 1年 門田未来、廣江実采、蔵野美結
〇場 所 3月21日~23日:京都府立ゼミナールハウス「あうる京北」
0 3月27日:毎日新聞東京本社・パレスサイドビル
理科部プラガールズが、3月の春休み中に2つの県外イベントに遠征しました。
3月21日~23日は、京都で開催された「地球環境ユースサミット2023 in KYOTO-持続可能な未来を議論する」(主催:京都超SDGsコンソーシアム、京都大学大学院地球環境学堂、共催:京都府)に、2年の村上さん、1年の門田さん、廣江さん、蔵野さんの4人が参加しました。これは国内外の高校生が3日間に渡り地球環境問題について話し合う合宿形式の国際会議で、使用言語は英語です。現地参加の50人とオンライン参加の100人(海外からの参加が多い)が各分科会に分かれ、大学生(留学生が多い)の補助を受けながら英語で議論を行いました。現地会場に泊り込みで参加したプラガールズの4人はそれぞれ別々の分科会に分かれ、英語に苦戦しながらも3日間の日程を有意義に過ごし、新しい仲間をつくることができました。
3月27日は、毎日新聞東京本社で行われた「イオンエコワングランプリ特別対談企画」に2年の村上さんと近藤さんが参加しました。2人は12月に東京で開催された「第11回イオンエコワングランプリ」(主催:イオンワンパーセントクラブ、共催:毎日新聞社、イオン環境財団)の最終審査会で発表し、研究・専門部門で内閣総理大臣賞を受賞しました。今回の企画は、本校プラガールズと普及・啓発部門で内閣総理大臣賞を受賞した三重県立明野高校の生徒が、最終審査員である五箇公一さん(国立環境研究所)と「持続可能な未来実現のために高校生ができること」について話し、全国の高校生に向けてメッセージを届ける記事になるものです。お互いに環境問題に取り組む思いを熱心に話し合い、非常に充実した対談をすることができました。五箇さんからは「高校生がここまで真剣に環境問題や自分の将来について考え、そのことをはっきりと自己主張できることに圧倒された」とのコメントをいただきました。記事の掲載は4月下旬になる予定です。
なお、3月30日、日本財団と(株)リバネスによる新年度の研究助成プログラム「マリンチャレンジプログラム2023」に、プラガールズが申請したテーマ「光エネルギーを利用した海洋性細菌の色素変化」が採択されました。
2023年3月25日 by admin
卓球部が合宿を実施しました
〇日 時 3月22日(水)~3月25日(土)
〇場 所 国立大洲青少年交流の家、八幡浜市民スポーツセンター
男女卓球部が国立大洲青少年交流の家を拠点として合宿をしました。
一日中卓球をするというだけでなく、夕食にバーベキューをしたり、ミーティング後にみんなでゲームをしたりして絆も深めてきました。途中、卒業生も参加して指導、アドバイスをしてくれました。また、南予、中予の高校との練習試合も行い、4月末にある総体へ向けて有意義な合宿となりました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |