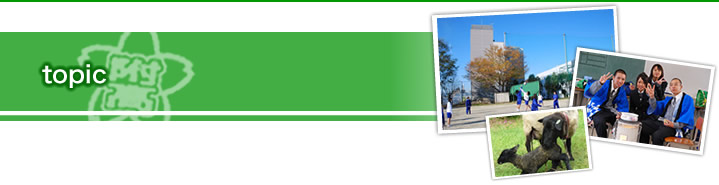
2024年9月18日 by admin
グローバル・スタディーズⅠを行いました
○ 日 時 令和6年9月18日(水)6・7限
○ 場 所 大講義室
○ 対 象 第2学年
○ 講 師 愛媛大学 宇宙プラズマ環境研究部門 宇宙進化研究センター 清水 徹 先生
今日のグローバル・スタディーズⅠは、「宇宙の謎:深宇宙探査機のはなし」と題して、清水 徹 先生にご講演をいただきました。「ロケットと探査衛星の仕組みからミスしない仕事(勉強)の進め方を考える」ことをテーマとすることに触れられました。神奈川県の宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所(ISAS)で科学探査衛星の管制業務に従事していたときのお話、映画にもなった「はやぶさ」についてのお話がありました。ロケットは運動量保存則に従い、燃料噴射の「反動(反作用)」で飛んでいる。多段ロケットは打ち上げと切り離しの効率を図っている。はやぶさ1の軌道は、スイングバイ航法(地球の重力アシスト)による省エネ飛行である。探査機は、太陽電池を充電可能にする危険回避のための自動制御モード(セーフホールドモード)を有している。様々な話題を物理の専門知識がない者にも理解できるように具体例を挙げながら熱く語っていただきました。休憩後、「あかつき」を金星の軌道に投入失敗した事例などをもとに、なぜ失敗したかを振り返り、対策を考えることの大切さをお話になりました。その後、事前課題として提示されていた「学校でも家庭でも、誰でもミスはします。あなたにとって日常生活でミスしないための工夫はありますか?どのようなときに、どんなミスをしますか?」について話し合いました。生徒からは、ネットに挙げる前にスマホのメモ機能を用いて、あらかじめ原稿を作成して、時間をおいて寝かして確認してから投稿する。相手の発言の復唱をしたり、パソコンとノートの二重チェックをしたりする。自分のキャパを理解して休養を取りながら生活する。ペットの世話を忘れないように、朝起きてすぐやるようにルーティンにしている。といった工夫が出されました。人間は必ずミスをする生き物ですが、先読みをしてミスを減らす。いろいろな方向から見つめてみる。間違い探しの工夫をする。忘れないためのルーティン作り。ファイル名に日づけを加えるなど、日常生活の中で工夫できることがあると改めて考えることができました。ご多用の中、清水 徹 先生、ありがとうございました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |